中島康晴
地域の絆 代表理事 中島康晴
社会関係の臨界
2014/08/24 21:18:06 社会全般
「論争」に投稿させて頂きました。
「9条の臨界」と題したコラム(「風速計」本誌1001号2014年7月25日)で、中島岳志氏が以下の様に述べている。「私は憲法9条に『他国防衛を旨とする集団的自衛権は行使しない』と明記すべきだと考えている。憲法に自衛隊の存在を記載し、国民の側から軍事力に縛りをかけるべきだ」。本文の全体を通じての氏のあるべき社会像や思想の本質には当然に共感している。しかし、如上の記載に対しては、やはり若干の違和感を抱かざるを得ない。議論を深めるために、筆を執ることにした。
たとえば、私は社会福祉実践家である。実践家が実践をなすには、その思想的な拠り所が必要である。また、その実践家が組織に所属している場合は、組織の共通理解(common sense)としての組織理念が最も重要であると日々考えている。なぜならば、実践家は日々現場の中で、その時々に起きている目の前の困難を克服すべく現実的な判断を迫られることが多く、その現実的な判断は、社会福祉実践家が拠り所とすべき価値・道徳的な判断とは齟齬が生じていることが往々にしてあるからだ。現場には、最低限定型化してやらざるを得ない業務があり、また現実的な関係や環境におけるしがらみがある。であればこそ、原理原則論や共通理解の確認が実践家には絶えず求められているのだと思う。
以上の様に、市井には、自らが置かれている現状・現実の中で、可能な実践を模索する経験的判断と、目的・未来に向けて私たちは何をすべきか・どうあるべきかを模索する価値・道徳的判断がある。特に実践家においてはその双方共に重要であるが、上記の如く、現場は、様々なしがらみに流されやすいので、時折立ち止まって価値・道徳的判断で自らの立ち位置を確認する作業が必要となる。
さて、憲法についてであるが、この2つの判断の内、経験的判断というよりは、価値・道徳的判断に依拠している様に思われる。社会福祉実践家が重要視すべき13条と25条はいまや瀕死の状態である。条文と現実のあいだには、かつて経験して事の無い大きな乖離が生じようとしている。であるならば、これらを現状に即して、実現可能なものに変えた方が良いのだろうか。そうはならないはずだ。
人々は今、画一化と多様性の喪失を基盤としながら、他者に対する関わりを忌避し、他者に対する慮りを喪失している。そこから、他者に対する無理解・不安・恐怖・軋轢・対立が生じ、加速度的に、他者に対する関わりに煩わしさを強めている。この負の循環の下にある現在の社会に求められていることは、人々の信頼の関係を再構築することであり、そのためには、あるべき社会に対する議論と模索が必要であると考える。あるべき社会とは何か。人々にその共通理解を促進する為に憲法は重要な役割を果たし得るはずだ。
9条に臨界が来ているのではない。人々の信頼の関係にこそ、臨界が生じているのである。その信頼の絆を取り戻すために、この社会の臨界を乗り越えるために、むしろ9条は有効な手段となり得ると私は認識している。
コメント
コメントはありません
当サイトで使用されている全ての画像および文章を無断で複製・転載・販売することを堅く禁じます。
すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright 特定非営利活動法人 地域の絆 All Rights Reserved.
すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
Copyright 特定非営利活動法人 地域の絆 All Rights Reserved.








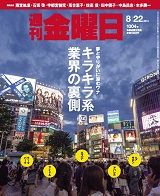


 RSS 2.0
RSS 2.0