ЁжФЬЄУЄЦЁЂЧёЄоЄьЄЦЁЂВШЄЫЄтЄЄЦЄЏЄьЄыЁзЁжНЛЄпДЗЄьЄПВШЄЧЃВЃДЛўДжЃГЃЖЃЕЦќЄЮАТПДЁзЁжЮзЕЁБўЪбЄЪТаБўЁЂМЋЮЉЛйБчЁЂАхЮХЄЮАТПДЁз

УцХчЙЏРВ
УЯАшЄЮхЋЁЁТхЩНЭ§ЛіЁЁУцХчЙЏРВ
ЁиБПБФПфПЪВёЕФЄЮЄЙЄЙЄсЪ§ЁйЁ
2009/11/29 12:00:00ЁЁЁЁУЯАшЬЉУхЗПЅЕЁМЅгЅЙ
ЁЁУЯАшЬЉУхЗПЅЕЁМЅгЅЙЁЂЦУЄЫОЎЕЌЬЯТПЕЁЧНЗПЕяТ№В№ИюЄЧЄЯЁЂБПБФОхЄЮКйЄЋЄЪЕЌРЉЄфРЉЬѓЄЌШѓОяЄЫОЏЄЪЄЄЄЮЄЌЄНЄЮЦУФЇЄЋЄШЛзЄяЄьЄоЄЙЁЃУцХљХйЄЋЄщНХХйЄЮРИГшВнТъЄђЪњЄЈЄЦЄЄЄщЄУЄЗЄуЄыЪ§ЄђЁЂНЛЄпДЗЄьЄПУЯАшЄфКпТ№ЄЧЛйЄЈЄЦЄЄЄЏЄПЄсЄЫЄЯЮзЕЁБўЪбЄЪЅБЅЂЁІЅЕЁМЅгЅЙЄЮКпЄъЪ§ЄЌЕсЄсЄщЄьЄыЄЮЄЯМЋЬРЄЮЄГЄШЄЧЄЙЄЋЄщЁЂЄГЄьЄЯХіСГЄЮЕЂЗыЄШЄтИРЄЈЄоЄЙЁЃАуЄУЄПЩНИНЄђЄЙЄьЄаЁЂЄНЄьЄРЄБЛіЖШНъТІЄЫБПБФЄЮКлЮЬИЂЄЌАбЄЭЄщЄьЄЦЄЄЄыЄГЄШЄЫЄЪЄъЄоЄЙЁЃ
ЁЁЄРЄЋЄщЄГЄНЁЂЛіЖШНъЄДЄШЄЫЮЩЄЏЄтАЄЏЄтЁжГЪКЙЁзЄЌРИЄИЄыЄГЄШЄЫЄЪЄъЄоЄЙЁЃУЯАшЬЉУхЗПЅЕЁМЅгЅЙЄЌСЯРпЄЕЄьЄЦЄтЄІФОЄА3ЧЏЄЫЄЪЄъЄоЄЙЄЌЁЂЅБЅЂЁІЅЕЁМЅгЅЙЄЮКпЄъЪ§ЁЂУЯАшЄШЄЮДиЗИРЁЂБПБФЄЮЛХЪ§ЄЫЛіЖШНъЄДЄШЄЮЦУПЇЄЌНаЄЦЄЄЦЄЄЄыЭЭЄЫИЋМѕЄБЄщЄьЄоЄЙЁЃУцЄЧЄтЁЂЦШМЋРЄЌЖЏЄЄЄЮЄЌБПБФПфПЪВёЕФЄЮКпЄъЪ§ЄЧЄЯЄЪЄЄЄЧЄЗЄчЄІЄЋЁЉ
ЁЁЄоЄКЁЂБПБФПфПЪВёЕФЄЮКпЄъЪ§ЄђЙЭЄЈЄыЄЫХіЄПЄУЄЦЁЂРЉХйОхЄЮЙЭЄЈЄЫПЈЄьЄЦЄЊЄЏЩЌЭзЄЌЄЂЄъЄоЄЙЁЃЁжЛиФъУЯАшЬЉУхЗПЅЕЁМЅгЅЙЄЮЛіЖШЄЮПЭАїЁЂРпШїЕкЄгБПБФЄЫДиЄЙЄыД№НрЁзЁЪИќРИЯЋЦЏОЪЮс ТшЃГЃДЙцЁЫЄфИќЯЋОЪЄЋЄщВсЕюЄЫНаЄЕЄьЄПЁжQЁѕAЁзЄЮЭзЛнЄђЄоЄШЄсЄыЄШПоЃБЄЮЄшЄІЄЫЄЪЄъЄоЄЙЁЃЄПЄУЄПЄГЄьЄРЄБЄЧЄЙЄЌЁЂЄГЄЮУцЄЋЄщЁЂИќРИЯЋЦЏОЪЄЌАеПоЄЙЄыЛіЪСЄфЁЂЛфЄПЄСЄЌЄГЄЮВёЕФЄђЭИњЄЫБПБФЄЗЄЦЄЄЄЏЪ§КіЄђИЋЄЄЄРЄЙЄГЄШЄЌНаЭшЄоЄЙЁЃЬЉММЄЧЄЮЅБЅЂЄЫДйЄъЄфЄЙЄЄЅАЅыЁМЅзЅлЁМЅрЄШОЎЕЌЬЯТПЕЁЧНЗПЕяТ№В№ИюЄЫТшЛАМдЄЮЩОВСЄЮЬмЄђФъДќХЊЄЫЦўЄьЁЂЅБЅЂЁІЅЕЁМЅгЅЙЄЮМСЄЮИўОхЄђСРЄУЄЦЄЄЄыЄЮЄЯИРЄІЄоЄЧЄтЄЂЄъЄоЄЛЄѓЄЌЁЂУцЄЧЄтЛфЄЯЁЂЁжЙНРЎАїЁзЄЮУцПШЄЫУэЬмЄЗЄЦЄЄЄоЄЙЁЃЭјЭбМдЄЮИЂЭјЭЪИюЄЌы№ЄяЄьЄЦЕзЄЗЄЄКЃЦќЭјЭбМдЁІВШТВЄЌЛВВУЄЙЄыЄЮЄЯМЋЬРЄЮЄГЄШЄЧЄЙЁЃЄНЄГЄЫЁЂУЯАшНЛЬБЄЮТхЩНМдЄфЁЂЙдРЏПІАїЁЂУЯАшЪёГчЛйБчЅЛЅѓЅПЁМПІАїЄЌЦўЄУЄЦЄЄЄыЄГЄШЄЫЛфЄЯЭЭЁЙЄЪВФЧНРЄШАеПоЄђДЖЄИЄЦЄЄЄоЄЙЁЃ
ЁЁЄоЄКУЯАшНЛЬБЄЮТхЩНМдЄЧЄЙЄЌЁЂИќЯЋОЪЄЮQЁѕAЄЧЄЯЁЂЁжФЎЦтВёЬђАїЁЂЬБРИАбАїЁЂЯЗПЭЅЏЅщЅжЄЮТхЩНМдХљЄЌЙЭЄЈЄщЄьЄыЁзЄШЩНИНЄЕЄьЄЦЄЄЄоЄЙЁЃЄГЄьЄщЄЮПЭЁЙЄЌВёЕФЄЫЛВВУЄЙЄыАеЕСЄфЁЂЄНЄЮЄГЄШЄЧЫОЄсЄыЄйЄХИЫОЄШЄЯЁЂЁУЯАшНЛЬБЄЌЛіЖШНъЄЮБПБФЄЫЛВВшЄЙЄыЄГЄШЂЛіЖШНъЁІУЯАшЪёГчЛйБчЅЛЅѓЅПЁМЁІЙдРЏЄЌУЯАшНЛЬБЄЮЅЫЁМЅКЄђЧФАЎЄЙЄыЄГЄШЃЛіЖШНъЁІУЯАшЪёГчЛйБчЅЛЅѓЅПЁМЁІЙдРЏЄШУЯАшНЛЬБЄЌЖЈЦЏЄЧЄоЄСЄХЄЏЄъЄђХИГЋЄЙЄыЄГЄШЁЂЄЌЕѓЄВЄщЄьЄоЄЙЁЃ
ЁЁИЖТЇЄШЄЗЄЦЁЂЦќОяРИГшЗїАшЦтЄЧДАЗыЄЙЄыЅЕЁМЅгЅЙФѓЖЁЄЌД№ЫмЄШЄЪЄыУЯАшЬЉУхЗПЅЕЁМЅгЅЙЄЫЄЊЄЄЄЦЁЂЄНЄЮЭјЭбМдЄЯУЯАшНЛЬБЄЧЄЂЄъЁЂБПБФПфПЪВёЕФЄЫУЯАшНЛЬБЄЮТхЩНМдЄЌЛВВУЄЙЄыЄГЄШЄЯЁЂОЭшМЋЪЌЄфВШТВЄЌЭјЭбЄЙЄыЄЧЄЂЄэЄІПШЖсЄЪЛіЖШНъЄђМЋЄщЄЮМъЄЧАщЄЦЁЂЄоЄПЩдШїЄЌЄЂЄьЄаЙдРЏЄЫЛиЦГАЭЭъЄђЙдЄІНЛЬБМЋМЃЄЫЗвЄЌЄыЄЮЄЧЄЯЄЪЄЄЄЋЄШЛфЄЯДќТдЄЗЄЦЄЄЄоЄЙЁЃ
ЁЁАьЪ§ЁЂУЯАшЪёГчЛйБчЅЛЅѓЅПЁМЄЫЄШЄУЄЦЄтЄГЄЮВёЕФЄЫЛВВУЄЙЄыАеЕСЄЯЄЂЄэЄІЄШЛзЄЄЄоЄЙЁЃЪПЖбЄЗЄЦЃВЁСЃГУцГиЙЛЖшЄђТаОнШЯАЯЄШЄЗЄЦГшЦАЄЙЄыУЯАшЪёГчЛйБчЅЛЅѓЅПЁМЄЌЁЂЃГЁСЃЖПЭФјХйЄЮПІАїЧлУжЄЧЁЂФОРмХЊЄЫУЯАшЛйБчЄђЙдЄІЄГЄШЄЌКЄЦёЄЪИНОѕЄђДеЄпЄьЄаЁЂЅЛЅѓЅПЁМДЩЦтЄЫЄЂЄыУЯАшЬЉУхЗПЅЕЁМЅгЅЙЄђОхМъЄЏЅГЁМЅЧЅЃЅЭЁМЅШЄЗЁЂДжРмХЊЄЪУЯАшЛйБчЄђМТСЉЄЗЄЦЄЄЄЏЛыХРЄтЩЌЭзЄЧЄЯЄЪЄЄЄЋЄШЙЭЄЈЄыЄЮЄЧЄЙЁЪПоЃВЁЫЁЃЄоЄПЁЂУЯАшЬЉУхЗПЅЕЁМЅгЅЙЄЮЅЭЅУЅШЅяЁМЅЏЄђУлЄЏЄГЄШЄтЁЂИјБзПЇЄЮЖЏЄЄУЯАшЪёГчЛйБчЅЛЅѓЅПЁМЄЫЄНЄЮДќТдЄЌДѓЄЛЄщЄьЄоЄЙЁЃ
ЁЁАЪОхЄЮЄшЄІЄЫБПБФПфПЪВёЕФЄЮЄЂЄъЪ§ЄђЙЭЄЈЄЦЄЄЄЏЄШЁЂЄНЄЮЬмХЊЄЯТчЄЄЏЃВЄФЄЂЄыЄЮЄЧЄЯЄЪЄЄЄЋЄШЙЭЄЈЄЦЄЄЄоЄЙЁЃЁГАЩєЄЮЛыХРЄђЦўЄьЁЂЅСЅЇЅУЅЏЕЁЧНЄђЦЏЄЋЄЛЅБЅЂЁІЅЕЁМЅгЅЙЄЮИўОхЄЫЗвЄВЄыЂУЯАшЄЮЅЫЁМЅКЄђЧФАЎЄЗЁЂЄНЄьЄЫБўЄЈЦРЄыЪ§КіЄђИЁЦЄЄЙЄыЁЃУЯАшЄЮхЋЄЮГЦЛіЖШНъЄЧЄЯЁЂЄГЄЮЃВЄФЄђОяЄЫ1ЁЇ1ЄЮЧлЪЌЄЧВёЕФЄЮБПБФЄђЙдЄЄЄоЄЙЁЃАЪВМУЯАшЄЮхЋЄЧЄЮМшЄъСШЄпЄШЁЂЄНЄГЄЋЄщИЋЄЈЄыБПБФПфПЪВёЕФЄЮВнТъЄЫЄФЄЄЄЦФѓИРЄЕЄЛЄЦЄтЄщЄЄЄоЄЙЁЃ
ЁЁЙНРЎАїЄЫЄФЄЄЄЦЄЯЁЂЭјЭбМдЁІЭјЭбМдЄЮВШТВЁІЛдПІАїЁІУЯАшЪёГчЛйБчЅЛЅѓЅПЁМПІАїЁІЖсЮйЛіЖШНъЁЪЕяТ№В№ИюЛйБчЛіЖШНъЄфВ№ИюЪнИБЛмРпХљЁЫЄЮПІАїЁІЛдМвВёЪЁЛуЖЈЕФВёПІАїЁІЪЁЛуЗЯРьЬчГиЙЛЙжЛеЁІМЋМЃВёФЙЁІЬБРИАбАїЁІЯЗПЭЅЏЅщЅжВёФЙЁІЖсЮйНЛЬБЄШЄЄЄУЄПЙНРЎЄЫЄЪЄУЄЦЄЄЄоЄЙЁЃУцЄЧЄтЁЂОЎЕЌЬЯТПЕЁЧНЗПЕяТ№В№ИюЄЮТаОнЭјЭбМдСќЄђЙЭЄЈЄыЄШЁЂЭјЭбМдЄЮЛВВУЄЌЦёЄЗЄЄЄГЄШЄЌВнТъЄШЄЪЄУЄЦЄЄЄоЄЙЁЃТОЄЮЛВВУМдЄЮЯУЄЮЦтЭЦЄђЭ§ВђЄЗЁЂЄДШЏИРЄЧЄЄыЪ§ЄЌШѓОяЄЫОЏЄЪЄЏЁЂЛВВУЄЕЄьЄыЄГЄШЄЯЕЉЄЫЄЗЄЋЄЂЄъЄоЄЛЄѓЁЃЄЧЄЂЄыЄЪЄщЄаЁЂЭјЭбМдЄЮИЂЭјЭЪИюЄђУДЪнЄЙЄыЪЬЄЮЕЁВёЄђРпЄБЄыЄЋЁЂЭјЭбМдЄЌЛВВУЄЧЄЄыВёЕФЄЮТЮРЉЄђРАЄЈЄыЄГЄШЄЌЩЌЭзЄРЄШЧЇМБЄЗЄЦЄЄЄоЄЙЁЃИЂЭјЭЪИюЄШЄЯЁЂЭјЭбМдЄЮМчТЮРЁІМЋШЏРЄђАњЄНаЄЗЁЂЄНЄЮПЭЄщЄЗЄЄРИГшЄђЛйБчЄЙЄыЄГЄШЄЧЄЂЄыЄШЛфЄЯЙЭЄЈЄЦЄЄЄоЄЙЁЃЄЧЄЂЄьЄаЄГЄНЁЂМЋЪЌЄПЄСЄЌЭјЭбЄЙЄыЛіЖШНъЄЮБПБФЄЫМчТЮХЊЄЫЛВВУЄЙЄыЕЁВёЄђЪнОуЄЙЄыЕСЬГЄЌЛфЄПЄСЄЫЄЯЄЂЄъЄоЄЙЁЃЭјЭбМдЄЌБПБФПфПЪВёЕФЄЫЛВВУЄЙЄыЄГЄШЄЮАеЕСЄђЄтЄУЄШТчРкЄЫЙЭЄЈЄПЄЄЄтЄЮЄЧЄЙЁЃ
ЁЁЄоЄПЁЂУЯАшНЛЬБЄЮТхЩНМдЄЫЄФЄЄЄЦЁЂЩЌЄКЄЗЄтМЋМЃВёЬђАїЄЮЪ§ЄШЄЄЄІТЊЄЈЪ§ЄЯЄЗЄЦЄЊЄъЄоЄЛЄѓЁЃЬђАїЄЮЪ§ЄЮЙЭЄЈЄЌЩЌЄКЄЗЄтУЯАшНЛЬБЄЮСэАеЄРЄШЄЯЙЭЄЈЄЦЄЄЄЪЄЄЄЋЄщЄЧЄЙЁЃМвВёЪЁЛуЖЈЕФВёЄЮПІАїЄЕЄѓЄЫЛВВУЄЄЄПЄРЄЄЄЦЄЄЄыЄЮЄЯЁЂЫЁПЭЄЮЭ§ЧАЄШМвВёЪЁЛуЖЈЕФВёЄЮЭ§ЧАЄЌАьУзЄЙЄыЄЋЄщЄЧЄЙЁЃЄЄЄКЄьЄЫЄЗЄЦЄтЁЂУЯАшНЛЬБЄђЄЯЄИЄсЁЂУЯАшЪёГчЛйБчЅЛЅѓЅПЁМЄфМвВёЪЁЛуЖЈЕФВёЁЂТОЛіЖШНъЄЫТаЄЗЄЦЁЂЛВВУЄђЄЊДъЄЄЄЙЄыАЭЭъЪИЄђЛ§ЛВЄЗЁЂЛіЖШНъЄЮЭ§ЧАЄђЄЗЄУЄЋЄъЄШРтЬРЄЕЄЛЄЦЄЄЄПЄРЄЏЄГЄШЄЌЩЌЭзЄЧЄЗЄПЁЃУЯАшНЛЬБЄЫТаЄЗЄЦЄЯНЛЬБРтЬРВёЄЮОьЄЧЁЂЛіЖШНъЄЫТаЄЗЄЦЄЯЃДЃАЪЌФјХйЄЮЅзЅьЅМЅѓЅЦЁМЅЗЅчЅѓЄђЄЕЄЛЄЦЄтЄщЄУЄЦЁЂЄНЄЮИхЛВВУЄЄЄПЄРЄЄЄПНъЄтЄЂЄъЄоЄЙЁЃУЯАшЬЉУхЗПЅЕЁМЅгЅЙЄЮПІАїЄЫЄЯКЃИхЁЂЖЏЄЏРтЬРЧНЮЯЄЌЕсЄсЄщЄьЄыЄГЄШЄЧЄЗЄчЄІЁЃИђОФЛіЄЮД№ЫмЄЯЁЂЅЧЁМЅПЁМЁІЭ§ЯРЁІО№ЦАРЄЧЄЂЄыЄШЛфЄЯМЋГаЄЗЄЦЄЄЄоЄЙЁЃУцЄЧЄтЁжО№ЦАРЁзЄЧЄЂЄыПДАеЕЄЄфЛзЄЄЄЌЄЪЄБЄьЄаЁЂТОМдЄЮПДЄђЦАЄЋЄЙЄГЄШЄЯНаЭшЄЪЄЄЄЧЄЗЄчЄІЁЃ
ЁЁМЁВѓЄЯЁЂВёЕФЄЮМТКнЄЫЄФЄЄЄЦЄЊЯУЄЗЄПЄЄЄШЛзЄЄЄоЄЙЁЃ
ПоЃБЁЁИќРИЯЋЦЏОЪЮсЄЫЄпЄыБПБФПфПЪВёЕФ
По2ЁЁУЯАшЪёГчЛйБчЅЛЅѓЅПЁМЄШУЯАшЬЉУхЗПЅЕЁМЅгЅЙЄЮДиЗИ
УЯАшЄЮхЋЄЫЄФЄЄЄЦЂ
2009/11/23 12:00:00ЁЁЁЁМвВёСДШЬ
ЁЁЄЪЄМЁЂКЃУЯАшЄЮхЋЄЌЕсЄсЄщЄьЄЦЄЄЄыЄЮЄЧЄЗЄчЄІЄЋЁЉЄНЄьЄЯЁЂЛ§ТГВФЧНЄЪНлДФЗПМвВёЄЌЕсЄсЄщЄьЛЯЄсЄЦЄЄЄыИНОѕЄШЁЂТчЄЄЄЫРАЙчРЄЌЄЂЄыЄшЄІЄЧЄЙЁЃ
ЁЁЫмЅжЅэЅАЄЧЄтЄЊЯУЄЗЄЦЄЄПЭЭЄЫЁЂМвВёЄЮЙНТЄЄфДиЗИРЄЮУцЄЧРИЄЄЦЄЄЄыЛфЄПЄСЄЫЄШЄУЄЦЁЂЁжЛфБзЁзЄШЁжИјБзЁзЄЯЫмЭшСъИпКюЭбЄЮДиЗИЄЫЄЂЄыЄЮЄЧЄЙЄЌЁЂИНТхМвВёЄЫЄЊЄЄЄЦЄНЄьЄЯРјКпВНЄЕЄьЁЂЄНЄІЄЧЄЯЬЕЄЄЄЋЄЮЧЁЄЏЁжСрКюЁзЄЕЄьЄЦЄЄПЄшЄІЄЫИЋМѕЄБЄщЄьЄоЄЙЁЃЄЪЄМЁЂЁжСрКюЁзЄЙЄыЩЌЭзЄЌЄЂЄыЄЮЄЋЄЯЁЂСГФјПМЄЄЙЭЛЁЄђЩЌЭзЄШЄЛЄКЄШЄтЁЂЛЁЄЗЄЌЄФЄЄоЄЙЁЃЗаКбЛъОхМчЕСЁІЖЅСшИЖЭ§МчЕСМвВёЄЫЄЊЄЄЄЦЄЯЁЂЁжЛфБзЁзЄШЁжИјБзЁзЄђЪЌЪЬЄЙЄыЄГЄШЄЌЄНЄЮСУЄШЄЪЄыЄЋЄщЄЧЄЗЄчЄІЁЃЄЄЄяЄцЄыЁЂОЁЄССШЄШЩщЄБСШЄђКюЄыЩЌЭзРЄЌЄЂЄУЄПЄЋЄщЄЧЄЯЄЪЄЄЄЧЄЗЄчЄІЄЋЁЃ
ЁЁЄЗЄЋЄЗЁЂЖсКЂЁЂМвВёЄЫГЪКЙЄЌЄЂЄыЄГЄШЄЯМТЄЯЁЂСДЙёЬБЄЫЄШЄУЄЦЮЩЄЏЄЪЄЄЄГЄШЄЧЄЯЄЪЄЄЄЋЄШЁЂЭ§ВђЄЕЄьЛЯЄсЄЦЄЊЄъЄоЄЙЁЃЄНЄГЄЧЁЂУэЬмЄђНИЄсЄЦЄЄЄыЄЮЄЌЁЂЛ§ТГВФЧНЄЪНлДФЗПМвВёЄЧЄЙЁЃ
ЁЁЄНЄтЄНЄтЁЂППЄЫЁжЫЄЋЄЪЁзМвВёЄШЄЯЁЂНлДФЗПЄЮМвВёЄНЄЮЄтЄЮЄЮЛіЄђИРЄІЄшЄІЄЧЄЙЁЃНлДФЄШЄЯЁЂМЋЪЌЄПЄСЄЮЙдЄЄЄЌЁЂНфЄъНфЄУЄЦЁЂЄЄЄКЄьЁЂЛвЄфТЙЄЮТхЄЫЁжЪжЄУЄЦЄЏЄыЁзЄГЄШЄђАеЬЃЄЗЄоЄЙЁЃМЋЬРЄЮЭ§ЄШЄЗЄЦЁЂЁжЛфБзЁзЄШЁжИјБзЁзЄЯНлДФЄЗЄЦЄЄЄыЄЮЄЧЄЙЁЃЄНЄЮЁжЪжЄУЄЦЄЏЄыЁзЛўДжКЙЄЫЁЂЭјБзЄђЮЋЄсМшЄыЄГЄШЄЌЄЧЄЄППЭЄђОЁЄССШЄШТЊЄЈЄЦЄтКЙЄЗЛйЄЈЄЪЄЄЄЮЄЋЄтУЮЄьЄоЄЛЄѓЄЭЁЃ
ЁЁЁжИјБзЁзЄШЁжЛфБзЁзЄђНлДФЄЕЄЛЄыЄНЄѓЄЪхЋЄђЄФЄЏЄУЄЦЄЄЄЄПЄЄЁЊЄНЄьЄГЄНЄЌЁЂУЏЄтЄЌМЋЪЌЄщЄЗЄЏАТПДЄЗЄЦЪыЄщЄЛЄыМвВёЙНУлЄиЄЮАьЮЄФЭЄШЄЪЄыЄЮЄЋЄтУЮЄьЄоЄЛЄѓЁЃУЯАшЄЮхЋЄЯЁЂЛ§ТГВФЧНЄЪНлДФЗПМвВёЄђЙНУлЄЙЄыПфПЪДяЄШЄЪЄыЄЮЄЧЄЗЄчЄІЄЋЁЉЄНЄІЄЂЄУЄЦЭпЄЗЄЄЄтЄЮЄЧЄЙЁЃ
ЁЁМуЧкРѕГиЄЮЛфЄЮЅГЅсЅѓЅШЄЧЄЯЪЊТЄъЄоЄЛЄѓЄЮЄЧЁЂКЧЖсЧвЦЩЄЗЄПЪИИЅЄшЄъЁЂАњЭбЄЕЄЛЄЦФКЄЄоЄЙЁЃ
ЁжАјБяЄШЄЯЁЂАјВЬДиЗИЄШБяЄЧЄЂЄыЁЃЄЙЄйЄЦЄЮЪЊЛіЄфТИКпЄЯЄФЄЪЄЌЄУЄЦЄЄЄЦЁЂИпЄЄЄЫАјЄЧЄЂЄъВЬЄЧЄЂЄыЁЃИФПЭЄЮИРЦАЄЯСДЄЦЁжАјЁзЄШЄЪЄъЁЂЩЌЄКЬЄЭшЄЫВПЄщЄЋЄЮБЦЖСЄђЭПЄЈЄыЁЃВПЄшЄъЁЂНлДФЄЗЄЦМЋЪЌЄЫЕЂЄУЄЦЄЏЄыЁЃЄНЄЮШПТаЄЌФОРўХЊЄЪЁжЬсЄУЄЦЭшЄЪЄЄЁЂНлДФЄЗЄЪЄЄЁзЛўДжЄЧЁЂЬсЄУЄЦЭшЄЪЄЄЄЋЄщЁжКЃЄЮЄІЄСЄЫЁзЭјБзЄђЄЋЄЙЄсМшЄУЄЦЄЊЄБЄаЁжОЁЄСЁзЄШЄЄЄІЙЭЄЈЄЫЄЪЄыЁЃЄНЄГЄЫЁЂМшЄУЄЦЄЗЄоЄЈЄыМдЁЪОЁЄФМдЁЫЄШЁЂМшЄУЄЦЄЗЄоЄЈЄЪЄЋЄУЄПМдЁЪЩщЄБЄПМдЁЫЄЌРИЄоЄьЄыЁЃЄГЄьЄЌЁЂЖсТхЄЮЁжЄЕЄтЄЗЄЕЁзЄЪЄЮЄРЁзЁЪЁиНЕДЉЖтЭЫЦќЁй2009.9.11.ЁЪ766ЙцЁЫЁжЩїТЎЗзЁзЁжЬЄЭшЄЮЄПЄсЄЮЙОИЭГиЁзХФУцЭЅЛвЛсЁЫЁЃ
ЁЁ
ЁЁЫмЅжЅэЅАЄЧЄтЄЊЯУЄЗЄЦЄЄПЭЭЄЫЁЂМвВёЄЮЙНТЄЄфДиЗИРЄЮУцЄЧРИЄЄЦЄЄЄыЛфЄПЄСЄЫЄШЄУЄЦЁЂЁжЛфБзЁзЄШЁжИјБзЁзЄЯЫмЭшСъИпКюЭбЄЮДиЗИЄЫЄЂЄыЄЮЄЧЄЙЄЌЁЂИНТхМвВёЄЫЄЊЄЄЄЦЄНЄьЄЯРјКпВНЄЕЄьЁЂЄНЄІЄЧЄЯЬЕЄЄЄЋЄЮЧЁЄЏЁжСрКюЁзЄЕЄьЄЦЄЄПЄшЄІЄЫИЋМѕЄБЄщЄьЄоЄЙЁЃЄЪЄМЁЂЁжСрКюЁзЄЙЄыЩЌЭзЄЌЄЂЄыЄЮЄЋЄЯЁЂСГФјПМЄЄЙЭЛЁЄђЩЌЭзЄШЄЛЄКЄШЄтЁЂЛЁЄЗЄЌЄФЄЄоЄЙЁЃЗаКбЛъОхМчЕСЁІЖЅСшИЖЭ§МчЕСМвВёЄЫЄЊЄЄЄЦЄЯЁЂЁжЛфБзЁзЄШЁжИјБзЁзЄђЪЌЪЬЄЙЄыЄГЄШЄЌЄНЄЮСУЄШЄЪЄыЄЋЄщЄЧЄЗЄчЄІЁЃЄЄЄяЄцЄыЁЂОЁЄССШЄШЩщЄБСШЄђКюЄыЩЌЭзРЄЌЄЂЄУЄПЄЋЄщЄЧЄЯЄЪЄЄЄЧЄЗЄчЄІЄЋЁЃ
ЁЁЄЗЄЋЄЗЁЂЖсКЂЁЂМвВёЄЫГЪКЙЄЌЄЂЄыЄГЄШЄЯМТЄЯЁЂСДЙёЬБЄЫЄШЄУЄЦЮЩЄЏЄЪЄЄЄГЄШЄЧЄЯЄЪЄЄЄЋЄШЁЂЭ§ВђЄЕЄьЛЯЄсЄЦЄЊЄъЄоЄЙЁЃЄНЄГЄЧЁЂУэЬмЄђНИЄсЄЦЄЄЄыЄЮЄЌЁЂЛ§ТГВФЧНЄЪНлДФЗПМвВёЄЧЄЙЁЃ
ЁЁЄНЄтЄНЄтЁЂППЄЫЁжЫЄЋЄЪЁзМвВёЄШЄЯЁЂНлДФЗПЄЮМвВёЄНЄЮЄтЄЮЄЮЛіЄђИРЄІЄшЄІЄЧЄЙЁЃНлДФЄШЄЯЁЂМЋЪЌЄПЄСЄЮЙдЄЄЄЌЁЂНфЄъНфЄУЄЦЁЂЄЄЄКЄьЁЂЛвЄфТЙЄЮТхЄЫЁжЪжЄУЄЦЄЏЄыЁзЄГЄШЄђАеЬЃЄЗЄоЄЙЁЃМЋЬРЄЮЭ§ЄШЄЗЄЦЁЂЁжЛфБзЁзЄШЁжИјБзЁзЄЯНлДФЄЗЄЦЄЄЄыЄЮЄЧЄЙЁЃЄНЄЮЁжЪжЄУЄЦЄЏЄыЁзЛўДжКЙЄЫЁЂЭјБзЄђЮЋЄсМшЄыЄГЄШЄЌЄЧЄЄППЭЄђОЁЄССШЄШТЊЄЈЄЦЄтКЙЄЗЛйЄЈЄЪЄЄЄЮЄЋЄтУЮЄьЄоЄЛЄѓЄЭЁЃ
ЁЁЁжИјБзЁзЄШЁжЛфБзЁзЄђНлДФЄЕЄЛЄыЄНЄѓЄЪхЋЄђЄФЄЏЄУЄЦЄЄЄЄПЄЄЁЊЄНЄьЄГЄНЄЌЁЂУЏЄтЄЌМЋЪЌЄщЄЗЄЏАТПДЄЗЄЦЪыЄщЄЛЄыМвВёЙНУлЄиЄЮАьЮЄФЭЄШЄЪЄыЄЮЄЋЄтУЮЄьЄоЄЛЄѓЁЃУЯАшЄЮхЋЄЯЁЂЛ§ТГВФЧНЄЪНлДФЗПМвВёЄђЙНУлЄЙЄыПфПЪДяЄШЄЪЄыЄЮЄЧЄЗЄчЄІЄЋЁЉЄНЄІЄЂЄУЄЦЭпЄЗЄЄЄтЄЮЄЧЄЙЁЃ
ЁЁМуЧкРѕГиЄЮЛфЄЮЅГЅсЅѓЅШЄЧЄЯЪЊТЄъЄоЄЛЄѓЄЮЄЧЁЂКЧЖсЧвЦЩЄЗЄПЪИИЅЄшЄъЁЂАњЭбЄЕЄЛЄЦФКЄЄоЄЙЁЃ
ЁжАјБяЄШЄЯЁЂАјВЬДиЗИЄШБяЄЧЄЂЄыЁЃЄЙЄйЄЦЄЮЪЊЛіЄфТИКпЄЯЄФЄЪЄЌЄУЄЦЄЄЄЦЁЂИпЄЄЄЫАјЄЧЄЂЄъВЬЄЧЄЂЄыЁЃИФПЭЄЮИРЦАЄЯСДЄЦЁжАјЁзЄШЄЪЄъЁЂЩЌЄКЬЄЭшЄЫВПЄщЄЋЄЮБЦЖСЄђЭПЄЈЄыЁЃВПЄшЄъЁЂНлДФЄЗЄЦМЋЪЌЄЫЕЂЄУЄЦЄЏЄыЁЃЄНЄЮШПТаЄЌФОРўХЊЄЪЁжЬсЄУЄЦЭшЄЪЄЄЁЂНлДФЄЗЄЪЄЄЁзЛўДжЄЧЁЂЬсЄУЄЦЭшЄЪЄЄЄЋЄщЁжКЃЄЮЄІЄСЄЫЁзЭјБзЄђЄЋЄЙЄсМшЄУЄЦЄЊЄБЄаЁжОЁЄСЁзЄШЄЄЄІЙЭЄЈЄЫЄЪЄыЁЃЄНЄГЄЫЁЂМшЄУЄЦЄЗЄоЄЈЄыМдЁЪОЁЄФМдЁЫЄШЁЂМшЄУЄЦЄЗЄоЄЈЄЪЄЋЄУЄПМдЁЪЩщЄБЄПМдЁЫЄЌРИЄоЄьЄыЁЃЄГЄьЄЌЁЂЖсТхЄЮЁжЄЕЄтЄЗЄЕЁзЄЪЄЮЄРЁзЁЪЁиНЕДЉЖтЭЫЦќЁй2009.9.11.ЁЪ766ЙцЁЫЁжЩїТЎЗзЁзЁжЬЄЭшЄЮЄПЄсЄЮЙОИЭГиЁзХФУцЭЅЛвЛсЁЫЁЃ
ЁЁ
ЅдЅѓЅСЄЯЅСЅуЅѓЅЙЁЊ
2009/11/18 12:00:00ЁЁЁЁМвВёСДШЬ
ЁЁПєЦќСАЁЂПМЬыШжСШЄЧЁЂЅеЅЃЅЎЅхЅЂЅЙЅБЁМЅШЁІЙтЖЖТчЪхСЊМъЄЮЩќГшЄЫЛъЄыЅЩЅЅхЅсЅѓЅПЅъЁМЄЌЪѓЄИЄщЄьЄЦЄЄЄоЄЗЄПЁЃ
ЁЁВМШОПШЄђЩщН§ЄЗЁЂКЦЕЏЄЙЄыЄоЄЧЁЂИЗЄЗЄЄЅъЅЯЅгЅъЄђЄГЄЪЄЗЁЂЖВЩнЄђЙюЩўЄЗЄЦЄЄЄЏЄНЄЮЛбЄЫЁЂЦБЄИПЭДжЄШЄЗЄЦЖЏЄЄДЖЦАЄђГаЄЈЄоЄЗЄПЁЃ
ЁЁЄЗЄЋЄЗЁЂЛфЄЌЖЏЄЏПДЄђЮБЄсЄПЄГЄШЄЯЁЂЅъЅЯЅгЅъЄђФЬЄЗЄЦЁЂАЪСАЄшЄъЄтВМШОПШЄЮНРЦ№РЄђЦРЄыЄГЄШЄЌЄЧЄЁЂКЃЄоЄЧАЪОхЄЮЄЗЄЪЄфЄЋЄЪЦАКюЄђМъЄЫЦўЄьЄПЄГЄШЁЃЄНЄЮЄГЄШЄЫТаЄЗЄЦЁЂЙтЖЖЛсМЋПШЄЌЁжВјВцЄђЄЗЄЦЮЩЄЋЄУЄПЁзЄШЯУЄЕЄьЄПЄГЄШЄЧЄЗЄПЁЃ
ЁЁЛфЄЯЁжЅдЅѓЅСЄЯЅСЅуЅѓЅЙЁзЄШЄЄЄІИРЭеЄђОяЄЫЁЂЪњЄЄЄЦЛХЛіЄђЄЗЄЦЄЄЄоЄЙЄЗЁЂПІАїЄЫЄтЄНЄЮЄшЄІЄЫХСЄЈЄЦЄЊЄъЄоЄЙЁЃЄНЄьЄЯЁЂЅдЅѓЅСЄђЅСЅуЅѓЅЙЄЫЪбЄЈЄыЛыХРЄГЄНЄЌЁЂПЭДжЄђЖЏЄЏРЎФЙЄЕЄЛЄыЄШПЎЄИЄЦЄЄЄыЄЋЄщЄЧЄЙЁЃЄоЄПЁЂЅдЅѓЅСЄђЅСЅуЅѓЅЙЄЫЪбЄЈЄыЄГЄШЄЌНаЭшЄыЄЋШнЄЋЄЫЁЂПЭДжЄШЄЗЄЦЄЮЁЂАьЄФЄЮЧНЮЯЄЮЁЂППВСЄЌЬфЄяЄьЄЦЄЄЄыЄШЙЭЄЈЄыЄЮЄЧЄЙЁЃЅдЅѓЅСЄђЅСЅуЅѓЅЙЄЫЪбЄЈЄыЄГЄШЄЌНаЭшЄыПЭДжЄГЄНЄЌЁЂЅзЅэЅеЅЇЅУЅЗЅчЅЪЅыЄЧЄЂЄыЄШЁЃ
ЁЁМЋПШЄЮПЎЧАЄђЛ§ЄУЄЦЁЂЅдЅѓЅСЄЫЮЉЄСИўЄЋЄУЄЦЄЄЄЏЛўЄЫЄГЄНЁЂЦРЄщЄьЄыЄтЄЮЄЯТчЄЄЄЄЯЄКЄЧЄЙЁЃЅдЅѓЅСЄЯЁЂПЭЄђЩЌЄКРЎФЙЄЫЦГЄЄоЄЙЁЃЄПЄРЄЗЁЂЄНЄЮЄПЄсЄЫЄЯЁЂМЋПШЄЫЖЏЄЄПЎЧАЄЌЄЪЄБЄьЄаЁЂЄНЄьЄЯУБЄЪЄыЅдЅѓЅСЄЧЄЗЄЋЄЂЄъЄоЄЛЄѓЁЃ
ЁЁВМШОПШЄђЩщН§ЄЗЁЂКЦЕЏЄЙЄыЄоЄЧЁЂИЗЄЗЄЄЅъЅЯЅгЅъЄђЄГЄЪЄЗЁЂЖВЩнЄђЙюЩўЄЗЄЦЄЄЄЏЄНЄЮЛбЄЫЁЂЦБЄИПЭДжЄШЄЗЄЦЖЏЄЄДЖЦАЄђГаЄЈЄоЄЗЄПЁЃ
ЁЁЄЗЄЋЄЗЁЂЛфЄЌЖЏЄЏПДЄђЮБЄсЄПЄГЄШЄЯЁЂЅъЅЯЅгЅъЄђФЬЄЗЄЦЁЂАЪСАЄшЄъЄтВМШОПШЄЮНРЦ№РЄђЦРЄыЄГЄШЄЌЄЧЄЁЂКЃЄоЄЧАЪОхЄЮЄЗЄЪЄфЄЋЄЪЦАКюЄђМъЄЫЦўЄьЄПЄГЄШЁЃЄНЄЮЄГЄШЄЫТаЄЗЄЦЁЂЙтЖЖЛсМЋПШЄЌЁжВјВцЄђЄЗЄЦЮЩЄЋЄУЄПЁзЄШЯУЄЕЄьЄПЄГЄШЄЧЄЗЄПЁЃ
ЁЁЛфЄЯЁжЅдЅѓЅСЄЯЅСЅуЅѓЅЙЁзЄШЄЄЄІИРЭеЄђОяЄЫЁЂЪњЄЄЄЦЛХЛіЄђЄЗЄЦЄЄЄоЄЙЄЗЁЂПІАїЄЫЄтЄНЄЮЄшЄІЄЫХСЄЈЄЦЄЊЄъЄоЄЙЁЃЄНЄьЄЯЁЂЅдЅѓЅСЄђЅСЅуЅѓЅЙЄЫЪбЄЈЄыЛыХРЄГЄНЄЌЁЂПЭДжЄђЖЏЄЏРЎФЙЄЕЄЛЄыЄШПЎЄИЄЦЄЄЄыЄЋЄщЄЧЄЙЁЃЄоЄПЁЂЅдЅѓЅСЄђЅСЅуЅѓЅЙЄЫЪбЄЈЄыЄГЄШЄЌНаЭшЄыЄЋШнЄЋЄЫЁЂПЭДжЄШЄЗЄЦЄЮЁЂАьЄФЄЮЧНЮЯЄЮЁЂППВСЄЌЬфЄяЄьЄЦЄЄЄыЄШЙЭЄЈЄыЄЮЄЧЄЙЁЃЅдЅѓЅСЄђЅСЅуЅѓЅЙЄЫЪбЄЈЄыЄГЄШЄЌНаЭшЄыПЭДжЄГЄНЄЌЁЂЅзЅэЅеЅЇЅУЅЗЅчЅЪЅыЄЧЄЂЄыЄШЁЃ
ЁЁМЋПШЄЮПЎЧАЄђЛ§ЄУЄЦЁЂЅдЅѓЅСЄЫЮЉЄСИўЄЋЄУЄЦЄЄЄЏЛўЄЫЄГЄНЁЂЦРЄщЄьЄыЄтЄЮЄЯТчЄЄЄЄЯЄКЄЧЄЙЁЃЅдЅѓЅСЄЯЁЂПЭЄђЩЌЄКРЎФЙЄЫЦГЄЄоЄЙЁЃЄПЄРЄЗЁЂЄНЄЮЄПЄсЄЫЄЯЁЂМЋПШЄЫЖЏЄЄПЎЧАЄЌЄЪЄБЄьЄаЁЂЄНЄьЄЯУБЄЪЄыЅдЅѓЅСЄЧЄЗЄЋЄЂЄъЄоЄЛЄѓЁЃ
УЯАшЄЮхЋЄЫЄФЄЄЄЦ
2009/11/15 12:00:00ЁЁЁЁМвВёСДШЬ
ЁЁШЗЛГЭГЕЊЩзМѓСъЄЌЁЂНъПЎЩНЬРБщРтЁЪ2009ЧЏ10Зю26ЦќЁЫЄЧЁжУЯАшЄЮхЋЁзЄШЄЄЄІИРЭеЄђЭбЄЄЄЦЁЂЄГЄьЄЋЄщЄЮМвВёЄЮКпЄъЪ§ЄЫЄФЄЄЄЦФѓИРЄЕЄьЄоЄЗЄПЁЃЁжЄГЄьЄоЄЧЦќЫмЄЮМвВёЄђЛйЄЈЄЦЄЄПУЯАшЄЮЁжЄЄКЄЪЁзЄЌЁЂКЃЄфЄКЄПЄКЄПЄЫРкЄъЮіЄЋЄьЄФЄФЄЂЄыЄЮЄЧЄЙЁЃЁЪУцЮЌЁЫЄЋЄФЄЦЄЮЁжУЏЄтЄЌУЏЄтЄђУЮЄУЄЦЄЄЄыЁзЄШЄЄЄІУЯБяЁІЗьБяЗПЄЮУЯАшЖІЦБТЮЄЯЁЂЄтЄЯЄфМКЄяЄьЄФЄФЄЂЄъЄоЄЙЁЃЁЪУцЮЌЁЫЁжЄЂЄЮЄЊЄИЄЄЄЕЄѓЄЯЁЂАьИЋЪаЖўЄНЄІЄРЄБЄЩЁЂЅмЅщЅѓЅЦЅЃЅЂЄЫЄЪЄыЄШОаДщЄЌЄЙЄЦЄЄЪЄѓЄРЁзЄШЄЋЁжЄЂЄЮЅжЅщЅИЅыПЭЄЯЁЂЬЕИ§ЄРЄБЄЩЁЂЅлЅѓЅШЄЯЄфЄЕЄЗЄЏЄЦЛвЄЩЄтЄЫЅЕЅУЅЋЁМЖЕЄЈЄыЄЮЄтЄІЄоЄЄЄѓЄРЄшЁзЄШЄЋЄЄЄУЄПЁЂЄНЄьЄОЄьЄЮВСУЭЄђЖІЭЄЙЄыЄГЄШЄЧЄФЄЪЄЌЄУЄЦЄЄЄЏЁЂПЗЄЗЄЄЁжЄЄКЄЪЁзЄђЄФЄЏЄъЄПЄЄЄШЙЭЄЈЄЦЄЄЄоЄЙЁзЁЃ
ЁЁКЧЖсЁЂДиРОЪ§ЬЬЄЫЫЌЄьЄПКнЁЂКИЄЮЄшЄІЄЪЅнЅЙЅПЁМЄђЬмЄЫГнЄБЄоЄЗЄПЁЃ
ЁЁЄоЄПЁЂЁжМвВёЄЮНъЦРГЪКЙЄЌТчЄЄЏЄЪЄыЄШЁЂЩЯКЄСиЄРЄБЄЧЄЪЄЏУцДжСиЄфЙтНъЦРСиЄЧЄтЛрЫДЄЙЄыДэИБРЄЌЙтЄоЄыЄГЄШЄЌЁЂЛГЭќТчЄЮЖсЦЃОАИЪНѕЖЕЄщЄЮТчЕЌЬЯЄЪЅЧЁМЅПЪЌРЯЄЧЪЌЄЋЄУЄПЁЃ
МвВёЄЮЄЄКЄЪЄЌЧіЄьЁЂЅЙЅШЅьЅЙЄЌЙтЄоЄыЄЮЄЌИЖАјЄщЄЗЄЄЁЃБбАхЛеВёЛяЄЫШЏЩНЄЗЄПЁзЁЪ2009ЧЏ11Зю21ЦќЦЩЧфПЗЪЙЁЫЁЃ
ЁЁКЃМвВёЄЫЄЯУЯАшЄЮхЋЄЌЁЂЖЏЄЏЕсЄсЄщЄьЄЦЄЄЄоЄЙЁЃЛфЄПЄСУЯАшЄЮхЋЄЯЁЂУЏЄтЄЌЁЂМЋЪЌЄщЄЗЄЏАТПДЄЗЄЦРИЄЄЦЄЄЄБЄыМвВёЄЮЙНУлЄђЬмЛиЄЗЄЦЁЂ2006ЧЏ2ЗюЄЫРпЮЉУзЄЗЄоЄЗЄПЁЃЦБЄИПЭДжЄШЄЗЄЦЁЂЙЭЄЈЪ§ЄЮАуЄЄЄђБлЄЈЄыЄГЄШЄђЗшЄЗЄЦФќЄсЄыЄГЄШЄЪЄЏЁЂТПЄЏЄЮЪ§ЁЙЄШТаЯУЄђТГЄБЁЂТчЄЄЪхЋЄђЄФЄЏЄыЄГЄШЄЧЁЂЄНЄЮЄшЄІЄЪМвВёЄЮЙНУлЄЌЄЧЄЄьЄаЄШЙЭЄЈЁЂМшЄъСШЄрЫшЦќЄЧЄЙЁЃ
ЁЁПЭЮрЄЌЖВЮЕЛўТхЄшЄъЄтФЙДќЄЫЄяЄПЄУЄЦЁЂУЯЕхОхЄЧРИЄБфЄгЄыЄПЄсЄЫЄЯЁЂУЯАшЄЮУцЄЧЁЂУЏЄтЄЌАТПДЄЗЄЦЪыЄщЄЛЄыМвВёЄђЙНУлЄЗЁЂГЦУЯЄЧУЯАшЄЮхЋЄђСЯТЄЄЗЁЂЄНЄьЄђСДРЄГІЄЫЙЄВЄЦЄЄЄЏЄГЄШЁЃЄГЄьЄЗЄЋЄЪЄЄЄШЁЂМЋПШЄЯЙЭЄЈЄЦЄЄЄоЄЙЁЃ
ЁЁЄНЄЮЄшЄІЄЪИиЄъЄђЪњЄЄЄЦЁЂЛфЄПЄСЄЯЁЂЙЙЄЪЄыюВПЪЄђЄЗЄЦЛВЄъЄПЄЄЄШЛзЄУЄЦЄЊЄъЄоЄЙЁЃВПЄшЄъЄтЁЂТПЄЏЄЮЪ§ЁЙЄШЄЮЖЏЄЄхЋЄђТчРкЄЫЁЃ
ЁЁ
ЁЁКЧЖсЁЂДиРОЪ§ЬЬЄЫЫЌЄьЄПКнЁЂКИЄЮЄшЄІЄЪЅнЅЙЅПЁМЄђЬмЄЫГнЄБЄоЄЗЄПЁЃ
ЁЁЄоЄПЁЂЁжМвВёЄЮНъЦРГЪКЙЄЌТчЄЄЏЄЪЄыЄШЁЂЩЯКЄСиЄРЄБЄЧЄЪЄЏУцДжСиЄфЙтНъЦРСиЄЧЄтЛрЫДЄЙЄыДэИБРЄЌЙтЄоЄыЄГЄШЄЌЁЂЛГЭќТчЄЮЖсЦЃОАИЪНѕЖЕЄщЄЮТчЕЌЬЯЄЪЅЧЁМЅПЪЌРЯЄЧЪЌЄЋЄУЄПЁЃ
МвВёЄЮЄЄКЄЪЄЌЧіЄьЁЂЅЙЅШЅьЅЙЄЌЙтЄоЄыЄЮЄЌИЖАјЄщЄЗЄЄЁЃБбАхЛеВёЛяЄЫШЏЩНЄЗЄПЁзЁЪ2009ЧЏ11Зю21ЦќЦЩЧфПЗЪЙЁЫЁЃ
ЁЁКЃМвВёЄЫЄЯУЯАшЄЮхЋЄЌЁЂЖЏЄЏЕсЄсЄщЄьЄЦЄЄЄоЄЙЁЃЛфЄПЄСУЯАшЄЮхЋЄЯЁЂУЏЄтЄЌЁЂМЋЪЌЄщЄЗЄЏАТПДЄЗЄЦРИЄЄЦЄЄЄБЄыМвВёЄЮЙНУлЄђЬмЛиЄЗЄЦЁЂ2006ЧЏ2ЗюЄЫРпЮЉУзЄЗЄоЄЗЄПЁЃЦБЄИПЭДжЄШЄЗЄЦЁЂЙЭЄЈЪ§ЄЮАуЄЄЄђБлЄЈЄыЄГЄШЄђЗшЄЗЄЦФќЄсЄыЄГЄШЄЪЄЏЁЂТПЄЏЄЮЪ§ЁЙЄШТаЯУЄђТГЄБЁЂТчЄЄЪхЋЄђЄФЄЏЄыЄГЄШЄЧЁЂЄНЄЮЄшЄІЄЪМвВёЄЮЙНУлЄЌЄЧЄЄьЄаЄШЙЭЄЈЁЂМшЄъСШЄрЫшЦќЄЧЄЙЁЃ
ЁЁПЭЮрЄЌЖВЮЕЛўТхЄшЄъЄтФЙДќЄЫЄяЄПЄУЄЦЁЂУЯЕхОхЄЧРИЄБфЄгЄыЄПЄсЄЫЄЯЁЂУЯАшЄЮУцЄЧЁЂУЏЄтЄЌАТПДЄЗЄЦЪыЄщЄЛЄыМвВёЄђЙНУлЄЗЁЂГЦУЯЄЧУЯАшЄЮхЋЄђСЯТЄЄЗЁЂЄНЄьЄђСДРЄГІЄЫЙЄВЄЦЄЄЄЏЄГЄШЁЃЄГЄьЄЗЄЋЄЪЄЄЄШЁЂМЋПШЄЯЙЭЄЈЄЦЄЄЄоЄЙЁЃ
ЁЁЄНЄЮЄшЄІЄЪИиЄъЄђЪњЄЄЄЦЁЂЛфЄПЄСЄЯЁЂЙЙЄЪЄыюВПЪЄђЄЗЄЦЛВЄъЄПЄЄЄШЛзЄУЄЦЄЊЄъЄоЄЙЁЃВПЄшЄъЄтЁЂТПЄЏЄЮЪ§ЁЙЄШЄЮЖЏЄЄхЋЄђТчРкЄЫЁЃ
ЁЁ
ЁиУЯАшЬЉУхЁІУЯАшИђЮЎЄђТЅПЪЄЙЄыЪ§ЫЁЄЁй
2009/11/12 12:00:00ЁЁЁЁУЯАшЬЉУхЗПЅЕЁМЅгЅЙ
ЁЁЛіЖШНъЄЌУЯАшЬЉУхЁІИђЮЎЄЙЄыЄГЄШЄЮКЧНЊЬмХЊЄЯЁЂУЏЄтЄЌМЋЪЌЄщЄЗЄЏАТПДЄЗЄЦЪыЄщЄЛЄыУЯАшЄХЄЏЄъЄЫЄЂЄыЄШЙЭЄЈЄоЄЙЁЃЬЕЯРЁЂЄНЄГЄЫЛъЄыЄоЄЧЄЫЄЯЄЄЄЏЄФЄЋЄЮУЪГЌЄђЗаЄЪЄБЄьЄаЄЪЄъЄоЄЛЄѓЁЃЮуЄЈЄаЁНЁНЁНЁПІАїЄШУЯАшНЛЬБЄЮПЦЬЉХйЄЮИўОхЁЂЂУЯАшНЛЬБЄЮЅЫЁМЅКЄЮЧФАЎЁЂЃЛіЖШНъЄЌУЯАшЁЪЙзИЅЁЫГшЦАЄђМТЛмЁЂЄУЯАшНЛЬБЄШЛіЖШНъЄЮПЎЭъДиЗИЄЮЙНУлЁЂЅУЯАшНЛЬБЄШЛіЖШНъЄЮЖЈЦЏДиЗИЄЮЙНУлЁЃЄГЄьЄщЄЮУЪГЌЄЫЄФЄЄЄЦЄЯЁЂМТСЉЅьЅйЅыЄЧЄоЄРЄоЄРЪ§ЫЁЯРЄЌГЮЮЉЄЗЄЦЄЄЄоЄЛЄѓЁЃАьЄФЄРЄБЬРЄщЄЋЄЪЄГЄШЄЯЁЂУЪГЌЄђСВМЁЦЇЄѓЄЧЙдЄЋЄЭЄаЁЂАьТШєЄгЄЫКЧНЊУЪГЌХўУЃЄЯНаЭшЄЪЄЄЄШЄЄЄІЄГЄШЄЧЄЗЄчЄІЁЃ
ЁЁЄЧЄЂЄыЄЋЄщЄГЄНЁЂУЯАшЄЮхЋЄЧЄЯЁЄђУЃРЎЄЙЄыЄПЄсЄЫЁжАЇЛЂБПЦАЁзЄђМТСЉЄЗЄЦЄЄоЄЗЄПЁЃПДЭ§ГиЄЮЮЮАшЄЧЄтЬРЄщЄЋЄЪЄшЄІЄЫЁЂАЇЛЂЄфЦќОяРИГшВёЯУЄђЄЙЄыПЦЬЉХйЄЮЅьЅйЅыЄЫУЃЄЗЄЪЄЄИТЄъЁЂЄНЄьАЪОхЄЮПЦЬЉЄЪДиЗИЄђУлЄЏЄГЄШЄЯНаЭшЄоЄЛЄѓЁЪПо1-1ЁІ2ЁЫЁЃЄЗЄЋЄЗЄЪЄЌЄщЁЂАЇЛЂЅьЅйЅыЄЮВёЯУЄЧЄЂЄьЄаЁЂЛіЖШНъЄЯЄЕЄлЄЩЯЋЮЯЄђЩщУДЄЛЄКЄШЄтЁЂПІАїЄвЄШЄъАьПЭЄЌАеМБЪбГзЄЕЄЈЄЙЄьЄаТЈМТСЉВФЧНЄЪЄтЄЮЄЧЄЙЁЃЅьЅйЅыЃВЄоЄЧЄЯЁЂЄЄЄШЄтЄПЄфЄЙЄЏМТСЉЄЌВФЧНЄЧЄЂЄыЄШИРЄЈЄоЄЙЁЃУЯАшЄЮхЋЄЧЄЯЄоЄКЁЂЅьЅйЅыЃВЄЮУЯАшНЛЬБЄШЄЮПЦЬЉХйЄђЙНУлЄЗЄЦЄЄоЄЗЄПЁЃЄГЄьЄЯЁЂВПЄЋЄђМТСЉЄЙЄыЄГЄШЄђЬмХЊЄЫПЦЬЉЄЫЄЪЄыЄЮЄЧЄЯЄЪЄЏЁЂПЦЬЉЄЫЄЪЄыЄГЄШМЋТЮЄђЬмХЊЄЫЄЗЄПМшЄъСШЄпЄЧЄтЄЂЄъЄоЄЙЁЃЄоЄКЄЯЁЂАьПЭЄЮПЭЄШЄЗЄЦНЛЬБЄШПЦЬЉЄЪДиЗИЄЫЄЪЄщЄЭЄаЁЂПЭЄШПЭЄШЄЌВПЄЋЄђЖЈЦЏЄЙЄыЄГЄШЄЫЄЯЗшЄЗЄЦЗвЄЌЄщЄЪЄЄЄЋЄщЄЧЄЙЁЃ
ЁЁЄНЄЗЄЦЁЂЄНЄЮОхАЬЅьЅйЅыЄЮПЦЬЉХйЄЌЙНУлЄЕЄьЄыЄЫЄФЄьЄЦЁЂЂЄЮМТСЉЄђЛюЄпЄоЄЗЄПЁЃЄГЄьЄЋЄщЄЊХСЄЈЄЙЄыЄЮЄЯЁЂУЯАшЄЮхЋЄЌБПБФЄЙЄыУЯАшЪЁЛуЅЛЅѓЅПЁМПЮИрЄЧМТСЉЄЗЄПЪ§ЫЁЄЧЄЙЄЌЁЂЄЩЄЮЛіЖШНъЄЧЄтМТСЉВФЧНЄЪЄфЄъЪ§ЄРЄШЛзЄЄЄоЄЙЄЮЄЧЁЂРЇШѓЛВЙЭЄЫЄЗЄЦЄЄЄПЄРЄБЄьЄаЄШЛзЄУЄЦЄЄЄоЄЙЁЃОЎЕЌЬЯТПЕЁЧНЄЮПІАїЄЌЁЂЅБЅЂЁІЖШЬГЄЫФЩЄяЄьЄыУцЄЧЁЂМТСЉВФЧНЄЪЪ§ЫЁЄђЙЭЄЈМшЄъСШЄѓЄРЄтЄЮЄЧЄЙЁЃПІАїЄЌУЯАшНЛЬБЄЫЪЙЄМшЄъЄђЙдЄІЄЮЄЧЄЙЄЌЁЂЄНЄЮКнЄЮЅыЁМЅыЄђАЪВМЄЊМЈЄЗЄЗЄоЄЙЁНЁН
ЁДќДжУцЁЪЃГНЕДжЄШЄЄЄІДќИТЄђРпЄБЄоЄЗЄПЁЫНаЖаЄЗЄППІАїЄЯ1ЦќХіЄПЄъЁЂЩбХй1ВѓАЪОхЁЂЛўДжЃЕЪЌАЪОхЁЂУЯАшНЛЬБЄШЦќОяРИГшВёЯУЄђЙдЄІ
ЂЈЭјЭбМдЄШЛЖЪтУцЄфЁЂСїЗоЄфЫЌЬфЛўЁЂНаТрЖаЛўЄЫМТЛмЁЃ
ЂЩсУЪЄЮЦќОяРИГшВёЯУЄШЄЯАуЄІЁЂВПЄщЄЋЄЮАеПоЄђЄтЄУЄПВёЯУЁЪУЯАшНЛЬБЄЮЅЫЁМЅКЄђАњЄНаЄЙВёЯУЁЫЄЧЄЂЄъЁЂЙЕСЄЮРИГшОьЬЬЬЬРмЄЧЄЂЄыЄШАЬУжЄХЄБЄыЁЃ
ЃЁжЅЫЁМЅКЄђАњЄНаЄЙВёЯУЁзЄШИРЄяЄьЄЦЄтЖёТЮХЊЄЫЭ§ВђЄЗЄЫЄЏЄЄЄПЄсЁЂЁЪУЯАшНЛЬБЄЌЁЫЁжКЄЄУЄЦЄЄЄыЄГЄШЁзЁжЫОЄѓЄЧЄЄЄыЄГЄШЁзЄђЪЙЄНаЄЙЄшЄІЄЫПІАїЄЫЛиЦГЄЙЄыЁЃЄПЄРЄЗЁЂЁжКЄЄУЄЦЄЄЄыЄГЄШЁзЁжЫОЄѓЄЧЄЄЄыЄГЄШЁзЄђФОРмЪЙЄЋЄКЄЫЁЂЦќОяВёЯУЄЮУцЄЋЄщЁжППАеЁзЄђЪЙЄМшЄыЄГЄШЄђЅыЁМЅыЄШЄЙЄыЁЃЂЈЭОФјДиЗИРЄЌНаЭшЄЦЄЄЄЪЄЄЄШЁЂФОРмЬфЄяЄьЄЦЄтУЯАшНЛЬБЄЯКЄЯЧЄЙЄыЁЃ
ЄМТЛмЄЗЄППІАїЄЯЁЂЕЯПЭбЛцЄЫВёЯУЄЮЦтЭЦЄђЕКмЄЙЄыЁЃЅпЁМЅЦЅЃЅѓЅАЭбЄЮЅлЅяЅЄЅШЅмЁМЅЩЄЫЭбЛцЄђХНЩеЄЗЁЂЄНЄЮЦќЄЮО№ЪѓЄђСДПІАїЄЧЖІЭЄЙЄыЁЃЂЈЖІЭЄЕЄьЄПО№ЪѓЄђЁЂМЁЄЮВёЯУЄЫГшЄЋЄЗЄЦЄЄЄЏЁЃ
ЅЪЙЄМшЄъФДККЄЋЄщЁЂОхЄЌЄУЄЦЄЄПЄтЄЮЄђKJЫЁЄЧЅЋЅЦЅДЅъЁМВНЄЙЄыЁЃ
АьЦќ5ЪЌФјХйЄЮВёЯУЄШЁЂЄНЄЮДќДжЄђЃГНЕДжЄЫИТФъЄЙЄыЄГЄШЄЧМТСЉЄЌВФЧНЄШЄЪЄъЁЂПоЃВЄЮЭЭЄЪЗыВЬЄђНаЄЙЄГЄШЄЌНаЭшЄоЄЗЄПЁЪЃГНЕДжЄЧЬѓЃГЃАВѓЄЮВёЯУЄђЕЯПЁЫЁЃ
ЁЁЄГЄьЄщЄЮЦтЁЂЛфЄПЄСЄЌИВУјЄЫМѕЄБЛпЄсЄПЄЮЄЌЁЂЁФЎЦтЄЮИђЮЎЂРЄТхДжЄЮИђЮЎЃЪИВНЄЮЗбОЕЄШЄМЋЪЌЄЮУЮМБЄфКЭЧНЄђГшЄЋЄЗЄПЄЄЁЂЄЧЄЗЄПЁЃЁЁСЃЄЯЄЩЄЮУЯАшЄЫЄтЖІФЬЄЙЄыЙрЬмЄЋЄтУЮЄьЄоЄЛЄѓЄЌЁЂПЮИрФЎЦтВёЁЪЅЛЅѓЅПЁМЄЌНъКпЄЙЄыМЋМЃВёЁЫЄтУЯАшГшЦАЛВВУМдЄЮЧЏЮ№СиЄђИЋЄыЄШЁЂ40ТхАЪВМЄЮЛВВУЮЈЄЌЅМЅэЄЫЖсЄЄОѕЖЗЄЧЄЗЄПЁЃЄЧЄЂЄыЄЋЄщЄГЄНЁЂУЯАшЪИВНЄфГшЦАЄЮХСОЕЁІЗбТГЄЫЩдАТЄЌЄЂЄУЄЦЩННаЄЕЄьЄПЅЫЁМЅКЄЧЄЂЄыЄШЙЭЄЈЄщЄьЄоЄЙЁЃЄЄЫДиЄЗЄЦЄЯЁЂМТЄЯУЯАшЙзИЅЄЌЄЗЄПЄЏЄЦЅІЅКЅІЅКЄЗЄЦЄЄЄыЄЌЁЂЄНЄьЄЌГшЦАЄЫЗыЄгЄФЄЄЄЦЄЄЄЪЄЄЅЫЁМЅКЄЌЄЂЄыЄГЄШЄђМЈЄЗЄЦЄЄЄоЄЙЁЃЄГЄьЄЯЁЂУЯАшЄЧКЄЄУЄЦЄЄЄщЄУЄЗЄуЄыЪ§ЁЪЭјЭбМдЁЫЄЮЛйБчЄђРьЬчПІЄЌАьЪ§ЄЧАњЄМѕЄБЄЪЄЌЄщЁЂЁжЛйБчЄЗЄПЄЄЁзЛзЄЄЄђЪњЄЈЄыНЛЬБЄЮЅЫЁМЅКЄђХйГАЛыЄЗЄЦЄЄЄыЄЌЄПЄсЄЫЁЂЮОМдЄЮЅоЅУЅСЅѓЅАЄЌЄЧЄЄКЄЫЄЄЄыСаЪ§ЄЫЄШЄУЄЦЁжЄтЄУЄПЄЄЄЪЄЄЁзИНОѕЄЌЄЂЄыЄГЄШЄђМЈЄЗЄЦЄЄЄоЄЙЁЃЄНЄЗЄЦЁЂГЮМТЄЫЅГЅпЅхЅЫЅЦЅЃЅБЅЂЄЮХкОэЄЌЄЂЄыЄГЄШЄђМТДЖНаЭшЄыЅЫЁМЅКЄЧЄтЄЂЄъЄоЄЙЁЃ
ЁЁЄНЄьЄђИЕЄЫЁЂУЯАшЪЁЛуЅЛЅѓЅПЁМПЮИрЄЧЄЯЁЂОЎУЯАшЛйБчЗзВшЄђКюРЎЄЗЄоЄЗЄПЁЃЄЧЄЙЄЋЄщЁЂСАЙцЄЧЪѓЙ№ЄЕЄЛЄЦЄЄЄПЄРЄЄЄПУЯАшИђЮЎЛіЖШЄШЄЗЄЦЄЮЅЄЅйЅѓЅШЄЯЁЂ40ТхАЪВМЄЮЧЏЮ№СиЄђУЯАшГшЦАЄЫДЌЄЙўЄѓЄЧЄЄЄЏЄГЄШЄђМчДуЄЫУжЄЄЄЦЄЮЦтЭЦЄШЄЗЄЦЄЊЄъЁЂЖёТЮХЊЄЫЛвЄЩЄтЄЮЗђСДАщРЎЄЫТаЄЙЄыЅЄЅйЅѓЅШЄђГЋКХЄЗЄЦЄЄЄоЄЙЁЃЛвЄЩЄтЄђТаОнЄЫЄЙЄыЄГЄШЄЧЁЂЛвЄЩЄтЄЮЮОПЦЄЫГшЦАЄЫЗШЄяЄУЄЦЄЄЄПЄРЄЏЄГЄШЄђСРЄУЄЦЄЮЄГЄШЄЧЄЙЁЃЄНЄЮЅЄЅйЅѓЅШЄђФЬЄЗЄЦЁЂДћТИЄЮУЯАшГшЦАЄЮУДЄЄМъЁЪ50КаАЪОхЄЮЪ§ЁЫЄШЁЂ40КаАЪВМЄЮНЛЬБЄШЄЮЅоЅУЅСЅѓЅАЄђЛХГнЄБЄыЄЮЄЧЄЙЁЃЫмЅЄЅйЅѓЅШЄђФЬЄЗЄЦЁЂ40ТхАЪВМЄЮЄЊЩуЄЕЄѓЄЌ2ЬОЁЂДћТИЄЮУЯАшГшЦАЄЫЛВВУЄЕЄьЄыЄшЄІЄЫЄЪЄъЄоЄЗЄПЁЃРЎВЬЄЯЄоЄРЄоЄРТчЄЄЏЄЂЄъЄоЄЛЄѓЄЌЁЂЄГЄІЄЄЄУЄПМшЄъСШЄпЄЯЗбТГРЄЌЩЌЭзЄРЄШЙЭЄЈЄЦЄЄЄоЄЙЁЃ
ЁЁУЯАшНЛЬБЄЮЅЫЁМЅКЄЯЁЂЛіЖШНъЄШНЛЬБЄЮПЦЬЉХйЄђОхЄВЄЦЄЄЄЏЅзЅэЅЛЅЙЄЧЁЂЭ§ВђЄЕЄьЄЦЄЏЄыЄШЛзЄЄЄоЄЙЄЌЁЂЄГЄСЄщТІЄЫУЯАшНЛЬБЄЮЅЫЁМЅКЄђУЕЄэЄІЄШЄЙЄыГЮЄЋЄЪАеЛзЄЌЄЪЄЄИТЄъЁЂУцЁЙТЊЄЈЄЫЄЏЄЄЄтЄЮЄРЄШЛзЄЄЄоЄЙЁЃЄоЄКЄЯЁЂМъУЕЄъЄЮУцЁЂУЯАшЄЫЭЭЁЙЄЪЛХГнЄБЄђХИГЋЄЗЁЂАьЪ§ЄЧЁжУЯАшНЛЬБЄЮЅЫЁМЅКЄЯВПЄЋЁЉЁзЄђОяЄЫЙЭЄЈЁЂНЛЬБЄЮЁжРМЁзЄЫМЊЄђнКЄЦЄыЩЌЭзЄЌЄЂЄыЄЮЄЧЄЯЄЪЄЄЄЧЄЗЄчЄІЄЋЁЃ
ЁЁЄНЄЮЄГЄШЄђПІАїЄЫХСЄЈЄыЄПЄсЄЫЄтЁЂИІНЄЄЮАьДФЄШЄЗЄЦЁЂУЯАшЪЁЛуЅЛЅѓЅПЁМПЮИрЄЮМшЄъСШЄпЄђЦГЦўЄЕЄьЄЦЄтЄшЄэЄЗЄЄЄЋЄШЛзЄЄЄоЄЙЁЃЄСЄЪЄпЄЫЁЂПЮИрЄЮМшЄъСШЄпЄЯЁЂШОЪЌЄЯЁЂПІАїЄЫУЯАшЄђТЊЄЈЄыЛыХРЄђЛ§ЄУЄЦЄтЄщЄІЄГЄШЄђЬмХЊЄЫИІНЄЄШЄЗЄЦМТСЉЄЗЄПЄтЄЮЄЧЄЙЁЃ
По1-1ЁЁАЇЛЂЕкЄгЦќОяРИГшВёЯУЄЮНХЭзР
По1-2ЁЁПДЭ§ГиЄЮЛыХРЄЋЄщЄЮПЦЬЉХйЅьЅйЅы
ЁЁЄЧЄЂЄыЄЋЄщЄГЄНЁЂУЯАшЄЮхЋЄЧЄЯЁЄђУЃРЎЄЙЄыЄПЄсЄЫЁжАЇЛЂБПЦАЁзЄђМТСЉЄЗЄЦЄЄоЄЗЄПЁЃПДЭ§ГиЄЮЮЮАшЄЧЄтЬРЄщЄЋЄЪЄшЄІЄЫЁЂАЇЛЂЄфЦќОяРИГшВёЯУЄђЄЙЄыПЦЬЉХйЄЮЅьЅйЅыЄЫУЃЄЗЄЪЄЄИТЄъЁЂЄНЄьАЪОхЄЮПЦЬЉЄЪДиЗИЄђУлЄЏЄГЄШЄЯНаЭшЄоЄЛЄѓЁЪПо1-1ЁІ2ЁЫЁЃЄЗЄЋЄЗЄЪЄЌЄщЁЂАЇЛЂЅьЅйЅыЄЮВёЯУЄЧЄЂЄьЄаЁЂЛіЖШНъЄЯЄЕЄлЄЩЯЋЮЯЄђЩщУДЄЛЄКЄШЄтЁЂПІАїЄвЄШЄъАьПЭЄЌАеМБЪбГзЄЕЄЈЄЙЄьЄаТЈМТСЉВФЧНЄЪЄтЄЮЄЧЄЙЁЃЅьЅйЅыЃВЄоЄЧЄЯЁЂЄЄЄШЄтЄПЄфЄЙЄЏМТСЉЄЌВФЧНЄЧЄЂЄыЄШИРЄЈЄоЄЙЁЃУЯАшЄЮхЋЄЧЄЯЄоЄКЁЂЅьЅйЅыЃВЄЮУЯАшНЛЬБЄШЄЮПЦЬЉХйЄђЙНУлЄЗЄЦЄЄоЄЗЄПЁЃЄГЄьЄЯЁЂВПЄЋЄђМТСЉЄЙЄыЄГЄШЄђЬмХЊЄЫПЦЬЉЄЫЄЪЄыЄЮЄЧЄЯЄЪЄЏЁЂПЦЬЉЄЫЄЪЄыЄГЄШМЋТЮЄђЬмХЊЄЫЄЗЄПМшЄъСШЄпЄЧЄтЄЂЄъЄоЄЙЁЃЄоЄКЄЯЁЂАьПЭЄЮПЭЄШЄЗЄЦНЛЬБЄШПЦЬЉЄЪДиЗИЄЫЄЪЄщЄЭЄаЁЂПЭЄШПЭЄШЄЌВПЄЋЄђЖЈЦЏЄЙЄыЄГЄШЄЫЄЯЗшЄЗЄЦЗвЄЌЄщЄЪЄЄЄЋЄщЄЧЄЙЁЃ
ЁЁЄНЄЗЄЦЁЂЄНЄЮОхАЬЅьЅйЅыЄЮПЦЬЉХйЄЌЙНУлЄЕЄьЄыЄЫЄФЄьЄЦЁЂЂЄЮМТСЉЄђЛюЄпЄоЄЗЄПЁЃЄГЄьЄЋЄщЄЊХСЄЈЄЙЄыЄЮЄЯЁЂУЯАшЄЮхЋЄЌБПБФЄЙЄыУЯАшЪЁЛуЅЛЅѓЅПЁМПЮИрЄЧМТСЉЄЗЄПЪ§ЫЁЄЧЄЙЄЌЁЂЄЩЄЮЛіЖШНъЄЧЄтМТСЉВФЧНЄЪЄфЄъЪ§ЄРЄШЛзЄЄЄоЄЙЄЮЄЧЁЂРЇШѓЛВЙЭЄЫЄЗЄЦЄЄЄПЄРЄБЄьЄаЄШЛзЄУЄЦЄЄЄоЄЙЁЃОЎЕЌЬЯТПЕЁЧНЄЮПІАїЄЌЁЂЅБЅЂЁІЖШЬГЄЫФЩЄяЄьЄыУцЄЧЁЂМТСЉВФЧНЄЪЪ§ЫЁЄђЙЭЄЈМшЄъСШЄѓЄРЄтЄЮЄЧЄЙЁЃПІАїЄЌУЯАшНЛЬБЄЫЪЙЄМшЄъЄђЙдЄІЄЮЄЧЄЙЄЌЁЂЄНЄЮКнЄЮЅыЁМЅыЄђАЪВМЄЊМЈЄЗЄЗЄоЄЙЁНЁН
ЁДќДжУцЁЪЃГНЕДжЄШЄЄЄІДќИТЄђРпЄБЄоЄЗЄПЁЫНаЖаЄЗЄППІАїЄЯ1ЦќХіЄПЄъЁЂЩбХй1ВѓАЪОхЁЂЛўДжЃЕЪЌАЪОхЁЂУЯАшНЛЬБЄШЦќОяРИГшВёЯУЄђЙдЄІ
ЂЈЭјЭбМдЄШЛЖЪтУцЄфЁЂСїЗоЄфЫЌЬфЛўЁЂНаТрЖаЛўЄЫМТЛмЁЃ
ЂЩсУЪЄЮЦќОяРИГшВёЯУЄШЄЯАуЄІЁЂВПЄщЄЋЄЮАеПоЄђЄтЄУЄПВёЯУЁЪУЯАшНЛЬБЄЮЅЫЁМЅКЄђАњЄНаЄЙВёЯУЁЫЄЧЄЂЄъЁЂЙЕСЄЮРИГшОьЬЬЬЬРмЄЧЄЂЄыЄШАЬУжЄХЄБЄыЁЃ
ЃЁжЅЫЁМЅКЄђАњЄНаЄЙВёЯУЁзЄШИРЄяЄьЄЦЄтЖёТЮХЊЄЫЭ§ВђЄЗЄЫЄЏЄЄЄПЄсЁЂЁЪУЯАшНЛЬБЄЌЁЫЁжКЄЄУЄЦЄЄЄыЄГЄШЁзЁжЫОЄѓЄЧЄЄЄыЄГЄШЁзЄђЪЙЄНаЄЙЄшЄІЄЫПІАїЄЫЛиЦГЄЙЄыЁЃЄПЄРЄЗЁЂЁжКЄЄУЄЦЄЄЄыЄГЄШЁзЁжЫОЄѓЄЧЄЄЄыЄГЄШЁзЄђФОРмЪЙЄЋЄКЄЫЁЂЦќОяВёЯУЄЮУцЄЋЄщЁжППАеЁзЄђЪЙЄМшЄыЄГЄШЄђЅыЁМЅыЄШЄЙЄыЁЃЂЈЭОФјДиЗИРЄЌНаЭшЄЦЄЄЄЪЄЄЄШЁЂФОРмЬфЄяЄьЄЦЄтУЯАшНЛЬБЄЯКЄЯЧЄЙЄыЁЃ
ЄМТЛмЄЗЄППІАїЄЯЁЂЕЯПЭбЛцЄЫВёЯУЄЮЦтЭЦЄђЕКмЄЙЄыЁЃЅпЁМЅЦЅЃЅѓЅАЭбЄЮЅлЅяЅЄЅШЅмЁМЅЩЄЫЭбЛцЄђХНЩеЄЗЁЂЄНЄЮЦќЄЮО№ЪѓЄђСДПІАїЄЧЖІЭЄЙЄыЁЃЂЈЖІЭЄЕЄьЄПО№ЪѓЄђЁЂМЁЄЮВёЯУЄЫГшЄЋЄЗЄЦЄЄЄЏЁЃ
ЅЪЙЄМшЄъФДККЄЋЄщЁЂОхЄЌЄУЄЦЄЄПЄтЄЮЄђKJЫЁЄЧЅЋЅЦЅДЅъЁМВНЄЙЄыЁЃ
АьЦќ5ЪЌФјХйЄЮВёЯУЄШЁЂЄНЄЮДќДжЄђЃГНЕДжЄЫИТФъЄЙЄыЄГЄШЄЧМТСЉЄЌВФЧНЄШЄЪЄъЁЂПоЃВЄЮЭЭЄЪЗыВЬЄђНаЄЙЄГЄШЄЌНаЭшЄоЄЗЄПЁЪЃГНЕДжЄЧЬѓЃГЃАВѓЄЮВёЯУЄђЕЯПЁЫЁЃ
ЁЁЄГЄьЄщЄЮЦтЁЂЛфЄПЄСЄЌИВУјЄЫМѕЄБЛпЄсЄПЄЮЄЌЁЂЁФЎЦтЄЮИђЮЎЂРЄТхДжЄЮИђЮЎЃЪИВНЄЮЗбОЕЄШЄМЋЪЌЄЮУЮМБЄфКЭЧНЄђГшЄЋЄЗЄПЄЄЁЂЄЧЄЗЄПЁЃЁЁСЃЄЯЄЩЄЮУЯАшЄЫЄтЖІФЬЄЙЄыЙрЬмЄЋЄтУЮЄьЄоЄЛЄѓЄЌЁЂПЮИрФЎЦтВёЁЪЅЛЅѓЅПЁМЄЌНъКпЄЙЄыМЋМЃВёЁЫЄтУЯАшГшЦАЛВВУМдЄЮЧЏЮ№СиЄђИЋЄыЄШЁЂ40ТхАЪВМЄЮЛВВУЮЈЄЌЅМЅэЄЫЖсЄЄОѕЖЗЄЧЄЗЄПЁЃЄЧЄЂЄыЄЋЄщЄГЄНЁЂУЯАшЪИВНЄфГшЦАЄЮХСОЕЁІЗбТГЄЫЩдАТЄЌЄЂЄУЄЦЩННаЄЕЄьЄПЅЫЁМЅКЄЧЄЂЄыЄШЙЭЄЈЄщЄьЄоЄЙЁЃЄЄЫДиЄЗЄЦЄЯЁЂМТЄЯУЯАшЙзИЅЄЌЄЗЄПЄЏЄЦЅІЅКЅІЅКЄЗЄЦЄЄЄыЄЌЁЂЄНЄьЄЌГшЦАЄЫЗыЄгЄФЄЄЄЦЄЄЄЪЄЄЅЫЁМЅКЄЌЄЂЄыЄГЄШЄђМЈЄЗЄЦЄЄЄоЄЙЁЃЄГЄьЄЯЁЂУЯАшЄЧКЄЄУЄЦЄЄЄщЄУЄЗЄуЄыЪ§ЁЪЭјЭбМдЁЫЄЮЛйБчЄђРьЬчПІЄЌАьЪ§ЄЧАњЄМѕЄБЄЪЄЌЄщЁЂЁжЛйБчЄЗЄПЄЄЁзЛзЄЄЄђЪњЄЈЄыНЛЬБЄЮЅЫЁМЅКЄђХйГАЛыЄЗЄЦЄЄЄыЄЌЄПЄсЄЫЁЂЮОМдЄЮЅоЅУЅСЅѓЅАЄЌЄЧЄЄКЄЫЄЄЄыСаЪ§ЄЫЄШЄУЄЦЁжЄтЄУЄПЄЄЄЪЄЄЁзИНОѕЄЌЄЂЄыЄГЄШЄђМЈЄЗЄЦЄЄЄоЄЙЁЃЄНЄЗЄЦЁЂГЮМТЄЫЅГЅпЅхЅЫЅЦЅЃЅБЅЂЄЮХкОэЄЌЄЂЄыЄГЄШЄђМТДЖНаЭшЄыЅЫЁМЅКЄЧЄтЄЂЄъЄоЄЙЁЃ
ЁЁЄНЄьЄђИЕЄЫЁЂУЯАшЪЁЛуЅЛЅѓЅПЁМПЮИрЄЧЄЯЁЂОЎУЯАшЛйБчЗзВшЄђКюРЎЄЗЄоЄЗЄПЁЃЄЧЄЙЄЋЄщЁЂСАЙцЄЧЪѓЙ№ЄЕЄЛЄЦЄЄЄПЄРЄЄЄПУЯАшИђЮЎЛіЖШЄШЄЗЄЦЄЮЅЄЅйЅѓЅШЄЯЁЂ40ТхАЪВМЄЮЧЏЮ№СиЄђУЯАшГшЦАЄЫДЌЄЙўЄѓЄЧЄЄЄЏЄГЄШЄђМчДуЄЫУжЄЄЄЦЄЮЦтЭЦЄШЄЗЄЦЄЊЄъЁЂЖёТЮХЊЄЫЛвЄЩЄтЄЮЗђСДАщРЎЄЫТаЄЙЄыЅЄЅйЅѓЅШЄђГЋКХЄЗЄЦЄЄЄоЄЙЁЃЛвЄЩЄтЄђТаОнЄЫЄЙЄыЄГЄШЄЧЁЂЛвЄЩЄтЄЮЮОПЦЄЫГшЦАЄЫЗШЄяЄУЄЦЄЄЄПЄРЄЏЄГЄШЄђСРЄУЄЦЄЮЄГЄШЄЧЄЙЁЃЄНЄЮЅЄЅйЅѓЅШЄђФЬЄЗЄЦЁЂДћТИЄЮУЯАшГшЦАЄЮУДЄЄМъЁЪ50КаАЪОхЄЮЪ§ЁЫЄШЁЂ40КаАЪВМЄЮНЛЬБЄШЄЮЅоЅУЅСЅѓЅАЄђЛХГнЄБЄыЄЮЄЧЄЙЁЃЫмЅЄЅйЅѓЅШЄђФЬЄЗЄЦЁЂ40ТхАЪВМЄЮЄЊЩуЄЕЄѓЄЌ2ЬОЁЂДћТИЄЮУЯАшГшЦАЄЫЛВВУЄЕЄьЄыЄшЄІЄЫЄЪЄъЄоЄЗЄПЁЃРЎВЬЄЯЄоЄРЄоЄРТчЄЄЏЄЂЄъЄоЄЛЄѓЄЌЁЂЄГЄІЄЄЄУЄПМшЄъСШЄпЄЯЗбТГРЄЌЩЌЭзЄРЄШЙЭЄЈЄЦЄЄЄоЄЙЁЃ
ЁЁУЯАшНЛЬБЄЮЅЫЁМЅКЄЯЁЂЛіЖШНъЄШНЛЬБЄЮПЦЬЉХйЄђОхЄВЄЦЄЄЄЏЅзЅэЅЛЅЙЄЧЁЂЭ§ВђЄЕЄьЄЦЄЏЄыЄШЛзЄЄЄоЄЙЄЌЁЂЄГЄСЄщТІЄЫУЯАшНЛЬБЄЮЅЫЁМЅКЄђУЕЄэЄІЄШЄЙЄыГЮЄЋЄЪАеЛзЄЌЄЪЄЄИТЄъЁЂУцЁЙТЊЄЈЄЫЄЏЄЄЄтЄЮЄРЄШЛзЄЄЄоЄЙЁЃЄоЄКЄЯЁЂМъУЕЄъЄЮУцЁЂУЯАшЄЫЭЭЁЙЄЪЛХГнЄБЄђХИГЋЄЗЁЂАьЪ§ЄЧЁжУЯАшНЛЬБЄЮЅЫЁМЅКЄЯВПЄЋЁЉЁзЄђОяЄЫЙЭЄЈЁЂНЛЬБЄЮЁжРМЁзЄЫМЊЄђнКЄЦЄыЩЌЭзЄЌЄЂЄыЄЮЄЧЄЯЄЪЄЄЄЧЄЗЄчЄІЄЋЁЃ
ЁЁЄНЄЮЄГЄШЄђПІАїЄЫХСЄЈЄыЄПЄсЄЫЄтЁЂИІНЄЄЮАьДФЄШЄЗЄЦЁЂУЯАшЪЁЛуЅЛЅѓЅПЁМПЮИрЄЮМшЄъСШЄпЄђЦГЦўЄЕЄьЄЦЄтЄшЄэЄЗЄЄЄЋЄШЛзЄЄЄоЄЙЁЃЄСЄЪЄпЄЫЁЂПЮИрЄЮМшЄъСШЄпЄЯЁЂШОЪЌЄЯЁЂПІАїЄЫУЯАшЄђТЊЄЈЄыЛыХРЄђЛ§ЄУЄЦЄтЄщЄІЄГЄШЄђЬмХЊЄЫИІНЄЄШЄЗЄЦМТСЉЄЗЄПЄтЄЮЄЧЄЙЁЃ
По1-1ЁЁАЇЛЂЕкЄгЦќОяРИГшВёЯУЄЮНХЭзР
ЁЪЫЁПЭСДЄЦЄЮПІАїЄЌЁЂЗбТГМТСЉЄЙЄыЄГЄШЄЌНХЭзЄЧЄЙЁЫ
По1-2ЁЁПДЭ§ГиЄЮЛыХРЄЋЄщЄЮПЦЬЉХйЅьЅйЅы
ЁЪЄоЄКЄЯЁЂЅьЅйЅы2ЄЮХўУЃЄђЬмЛиЄЗЄоЄЗЄчЄІЁЊЁЫ
По2ЁЁУЯАшНЛЬБЄЮЅЫЁМЅКЄШЄЯЁЊЁЉ
Page 1 / 2
ХіЅЕЅЄЅШЄЧЛШЭбЄЕЄьЄЦЄЄЄыСДЄЦЄЮВшСќЄЊЄшЄгЪИОЯЄђЬЕУЧЄЧЪЃРНЁІХОКмЁІШЮЧфЄЙЄыЄГЄШЄђЗјЄЏЖиЄИЄоЄЙЁЃ
ЄЙЄйЄЦЄЮЦтЭЦЄЯЦќЫмЄЮУјКюИЂЫЁЕкЄгЙёКнОђЬѓЄЫЄшЄУЄЦЪнИюЄђМѕЄБЄЦЄЄЄоЄЙЁЃ
Copyright ЦУФъШѓБФЭјГшЦАЫЁПЭЁЁУЯАшЄЮхЋ All Rights Reserved.
ЄЙЄйЄЦЄЮЦтЭЦЄЯЦќЫмЄЮУјКюИЂЫЁЕкЄгЙёКнОђЬѓЄЫЄшЄУЄЦЪнИюЄђМѕЄБЄЦЄЄЄоЄЙЁЃ
Copyright ЦУФъШѓБФЭјГшЦАЫЁПЭЁЁУЯАшЄЮхЋ All Rights Reserved.








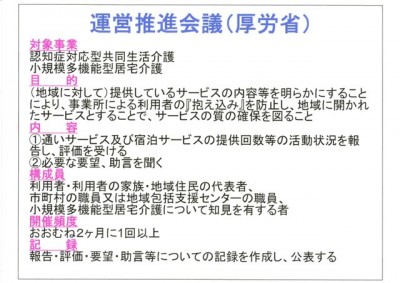
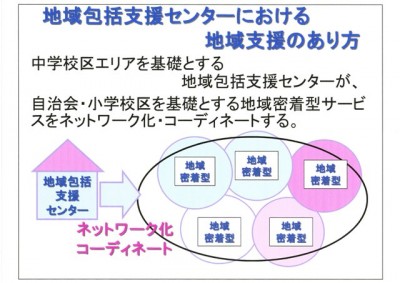


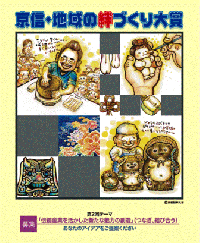

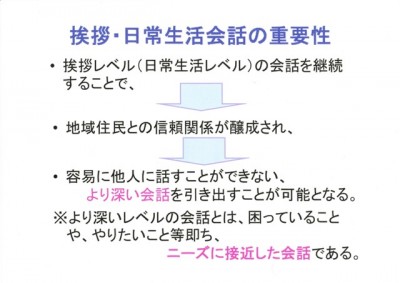
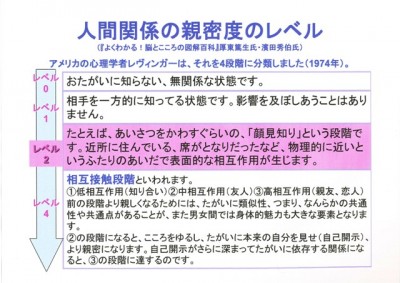
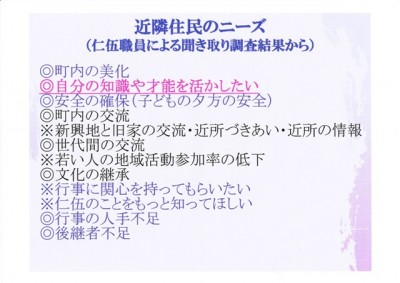

 RSS 2.0
RSS 2.0